「ブランデー」とは、おもに白ブドウなどの果実を発酵させた果実酒を蒸留して作るアルコール飲料です。 蒸留直後の蒸留液は無色透明ですが、木製の樽に詰められ熟成することにより琥珀色になるとともに豊かな風味に仕上がります。 蒸留
「ブランデー」と「コニャック」の違いは?


「ブランデー」とは、おもに白ブドウなどの果実を発酵させた果実酒を蒸留して作るアルコール飲料です。 蒸留直後の蒸留液は無色透明ですが、木製の樽に詰められ熟成することにより琥珀色になるとともに豊かな風味に仕上がります。 蒸留

「海の日」、「山の日」は、いずれも国民の祝日に関する法律で定められた日本の国民の祝日です。 「海の日」とは、1995年(平成7年)に制定され、1996年(平成8年)から施行された日本の国民の祝日のひとつで、日付は施行当初

「水上オートバイ」とは、船体下部の吸入口から取り入れた水を高圧で後方に噴出する事によって推進力を得る「ウォータージェット推進」を用いた水上の乗り物で、日本の法律では「特殊小型船舶」に分類されます。 「水上オートバイ」には

「乳児」、「幼児」、「児童」は、児童福祉法において以下のように定義されています。 「乳児」とは、児童福祉法第4条第1項で「生後1年未満の者」と定義されており、生後すぐから満1歳になるまでの子供のことをいいます。 母子保健

「国民の祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」で定められた日本の祝日で、固有の名称を持つ「国民の祝日」は現在以下の通りです。 1月1日 元日 1月の第2月曜日 成人の日 2月11日 建国記念の日 3月20〜21日頃 春分

自動車の利用において、万が一の事故の際に損害を補償する自動車保険には、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」があります。 「自賠責保険」とは、自動車損害賠償保障法により自動車および原動

「行政書士」、「司法書士」は、いずれも法律にのっとった書類作成をおもな仕事とする職業です。 「行政書士」とは、総務省が管轄する、行政書士法に基づいた国家資格で、国の機関や都道府県、市町村などの行政機関に提出する書類の作成
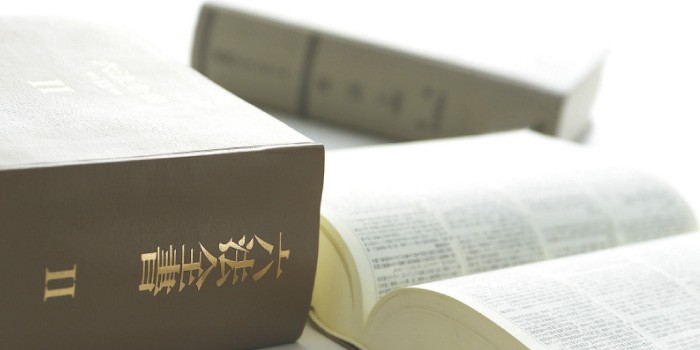
「未必の故意(みひつのこい)」、「認識ある過失(にんしきあるかしつ)」は、いずれも法律用語です。 「未必の故意」とは、自分の行為によって違法状態に至る可能性を認識しており、結果的に犯罪行為が発生してもかまわないとい

「接骨院」とは、国家資格を持つ柔道整復師が、骨、関節、筋、腱、靭帯などに発生した骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲などの損傷に対し、柔道整復術による治療を行う施術所です。 「接骨院」の名称は、柔道整復師しか使用できません。

法令上、成年(20歳)に満たない未成年や、児童のことを「こども」といいます。 また、親との相対的関係を表す言葉としても「こども」が使用されます。 「こども」は人間以外の動物にも使われ、生物に限らず大きいものと小さいものが