「お盆」、「お彼岸」は、いずれも日本における伝統的な宗教行事期間ですが、それぞれ別の期間を指します。 「お盆」とは、日本において先祖の霊を祀る伝統的な行事期間で、一般的に8月13日から16日の期間を指します。 「お盆」は
「お盆」と「お彼岸」の違いは?


「お盆」、「お彼岸」は、いずれも日本における伝統的な宗教行事期間ですが、それぞれ別の期間を指します。 「お盆」とは、日本において先祖の霊を祀る伝統的な行事期間で、一般的に8月13日から16日の期間を指します。 「お盆」は

「端午の節句」、「こどもの日」は、いずれも5月5日のことを指しますが、それぞれ別の意味を持ちます。 「端午の節句」とは、5月5日に男子の成長を祝って健康を願う伝統行事・風習のことで「たんごのせっく」と読みます。 伝統的な

「メリークリスマス」とは、クリスマスを祝う挨拶の定番で、英語での綴りは “Merry Christmas” 、直訳すると「よいクリスマスを!!」といった意味になります。 「クリスマス」は本来「キリ

「ハロウィン」とは、毎年10月31日に行われる行事のことで、古代ケルト人による秋の収穫を祝う祭りがその発祥とされています。 もともとは悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事でしたが、現代ではクリスマスに次ぐ民間行事

「クリスマス」とは、キリスト教における救世主イエス・キリストの降誕祭(生まれてきたことを祝う日でキリストの誕生日ではない)で、日本においては12月25日終日とされるのが一般的です。 英語での綴りは “Chri

「ブラックフライデー」とは、アメリカ合衆国の祝日である「感謝祭(11月の第4木曜日)」の翌日の金曜日のことです。 作物の収穫を祝う感謝祭は、アメリカでは親族や友人が集まる大切な家族行事となっており、感謝の意を込めてプレゼ
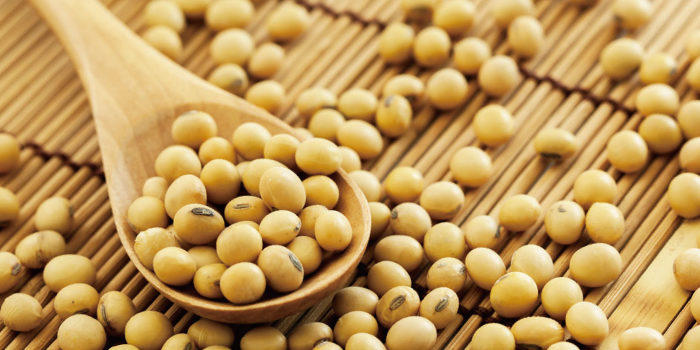
「大豆」とは、マメ科ダイズ属の一年草で、種子を食用とする穀類のひとつで「だいず」と読みます。 乾燥した「大豆」の種子は薄茶色で、直径は8~10mm程度と豆類の中で極端に大きい部類とはいえないため、名前の由来は明確になって

「春の七草」とは、1月7日の「人日の節句」に、厄払いや無病息災の願いを込めて食べる「七草粥」に入れられる7種の野菜「せり」「なずな」「ごぎょう」「はこべら」「ほとけのざ」「すずな」「すずしろ」のことです。 「七草粥」には

「正月」とは、本来は旧暦1月の別名で、その年の最初の月である1月全部を指しますが、現在では新年を祝う期間や、年初の行事そのものを指す場合が多いです。 「正月」の指す期間に、明確な定義はありませんが、多くの場合1月1日~3

一年の初めに神社や寺院を参拝し、旧年の感謝を捧げたり、新年の無事と平安を祈願する「初詣」は、元々は大晦日の夜から元日の朝にかけて社に籠る「年籠り」という行事に由来します。 「年越し参り」、「二年参り」は、いずれも「初詣」